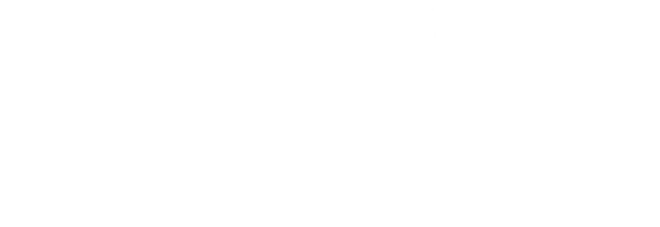境内のご案内
当神社の境内は、四季折々の美しい自然に彩られ、訪れるたびに新たな発見がございます。春には満開の桜が舞い、夏には青々とした木々が涼をもたらし、秋には鮮やかな紅葉が境内を染め、冬には静寂の中に雪景色が広がります。特に京都嵐山から移植された境内の紅葉は「五彩のもみじ」と称賛され、赤、橙、黄、黄緑、緑の5色に彩られます。境内では写真撮影も可能ですので、季節ごとの風景や伝統的な建築物をカメラに収めていただけます。
-

①大鳥居脇北畠顕家公銅像
-

②表参道256段の石階段
-

③手水舎
-

④参拝者休憩所
-

⑤鳴龍館
皇室の方々がお使いになられる「鳴龍館」。
入口には「霊山鳴龍開運神」という札が掲げられ、この館には鳴龍(なきりゅう)がお住まいになられているといわれています。その鳴龍の名前は「八大龍王」と言われ、館の入り口で手をたたくと自身の龍の鳴声を聴くことができます。さらに赤龍の刺繍額に自身の鳴龍が飛んでいくことから、「飛び龍」も体験できます。 -

⑥神門
-

⑦神楽殿
-

⑧参道脇五色の紅葉
京都にお住まいだった北畠顕家公の御霊の安寧を祈り嵐山から移植され、東北にはない紅葉の色が境内を彩ります。
社殿脇の紅葉は「いろは紅葉」といい、一本で五色の色を楽しむことができます。 -

⑨貫通石
トンネルを掘削して全線貫通する際、最後に掘られた貴重な岩片です。平成23年3月11日に発生した東日本大震災からの復興支援道路として建設された国道115号線高規格自動車専用霊山道路で、平成27年10月10日に貫通した「七ツ窪トンネル」と10月27日に貫通した「庄司渕トンネル」の貫通石です。
貫通石は願い事が貫通するということから奈良時代以前から珍重されています。 -

⑩社殿
明治14年に明治政府(国費)で建立。
明治13年6月に着工し、明治14年5月11日に竣工。
明治18年4月22日に別格官幣社に認可。 -

⑪本殿
-

⑫福日稲荷神社
-

⑬祖霊社