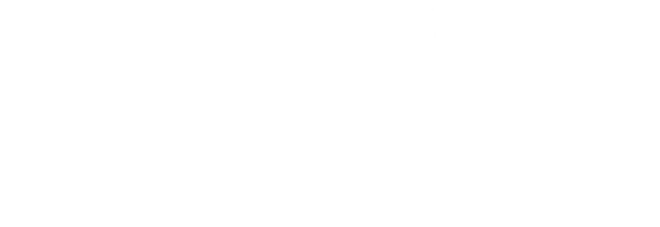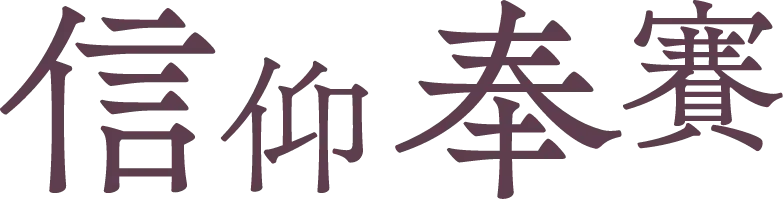由緒・沿革
当神社は、北畠一族が祀られている神社です。明治14年、北畠顕家、親房、顕信、守親(顕信の子)を主祭神として、北畠氏の支城があった地に創建されました。建武の新政に尽力した南朝側の皇族、武将を祀る15の神社(建武中興十五社)のひとつに数えられています。
そして、境内には北畠顕家公の御霊の安寧を祈り、京都嵐山から移植された「五色の紅葉」はたくさんの御参拝の皆様に喜ばれています。

- 北畠守親公
- 北畠顕信公
- 北畠親房公
- 北畠顕家公
約680年前、武家の権力争いによって日本の政治は混乱し、国民生活も不安定な状況にありました。後醍醐天皇は、国の秩序を回復し国民の幸福を増進するため「建武の中興」を行い、北畠顕家公をはじめとする方々がこの大業に尽力しました。顕家公は16歳で陸奥介に任命され、父・親房公とともに東北地方で後醍醐天皇の息子・義良親王を支えましたが、21歳の若さで戦死しました。弟の顕信公や息子の守親公も皇統護持に貢献しました。明治時代には「明治維新の根本理念は建武中興にある」とされ、北畠一門を祀る神社創建の機運が高まりました。明治天皇が東北巡幸で霊山を拝したことを契機に、1879年に霊山神社が創建され、1885年に別格官幣社となりました。

霊山の麓に北畠一族が祀られている神社です。明治14(1881)年、北畠顕家、親房、顕信、守親(顕信の子)を主祭神として、北畠氏の支城があった地に創建されました。建武の新政に尽力した南朝側の皇族、武将を祀る15の神社(建武中興十五社)のひとつに数えられています。京都の嵐山から移植されたという紅葉の美しさと、春の例大祭に奉納される剣舞「濫觴武楽(らんじょうぶがく)」や「大石北又獅子舞」で知られています。